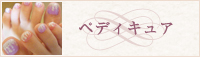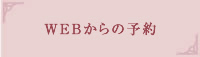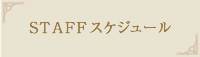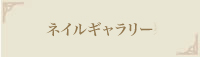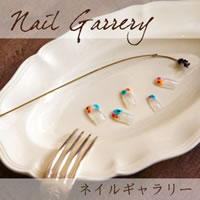アジアにおけるネイルの進化
中国では、古くから「爪染め」が行われており、遊牧民の婦女たちも
「紅粧」(こうしょう)と「爪紅」(つめべに)を行っていた事が明らかに
されています。
その後、宮廷において衣装や刺繍の絵柄、化粧法、爪の長さ等は
身分階級を表す重要なものへと変わっていきます。
また、蜜蝋と卵白、ゼラチン、アラビアゴムなどをつかって
占領を作り出し、期限是院600年になると、皇族は金や銀を
爪に塗るようになりました。
また、西太后が小指と薬指に緑(翡翠)の長い爪(護指)をつけている絵画があり、
中国では18世紀に既に付け爪=護指がありました。
それは目を見張るほどの高度な技術を持って作られています。
更に、裕福な位にある男女共に小指と薬指の爪を長くする風習が
あったそうです。
長い爪は手仕事をしない高貴な身分の証と考えられていたそうです。
マニキュアリストの登場
近代・19世紀、欧米ではいよいよ一般女性にも身だしなみとしての
マニキュアが浸透し始めます。
蜜蝋や油などを研磨剤として使い、セーム皮で磨く方法などで、ナチュラルで
すけるようなピンク色のネイルがもてはやされます。
また、おしゃれからマナーとしてのネイルが額率し始め、職業としての
マニキュアリストが登場します。
更に、ネイルの道具(マニキュア箱)なども販売され始めますが、
非常に高価でまだ庶民にとって身近なものとは言えませんでした。
ギリシャ・ローマ時代~中世・ルネッサンス時代
ギリシャ・ローマ時代においては上流階級の中で、「マヌス・キュア」という
言葉が生まれ流行していきます。
この時代においてはエーゲ海に臨むギリシャが、もともと世界で最初の文化が
発生したと言われるオリエント文化と早くから海上貿易を行っていたことから
その文化の影響を受けて後にエーゲ文明が生まれました。
当時のギリシャの女性は控えめな生活が望まれ、健康的な美を理想とし、
人工的な美は好まなかったと言います。
そんな背景から、お手入れとしてのマニキュアが流行したことが理解できます。
さらに、中世・ルネッサンス時代になると階級層の成り立ちの影響から、
芸術、文化が発達し、中でも舞台芸術が化粧の文化を高めていきます。
オペラの期限となるバレエが創作され、キャラクターを演じる上で演出としての
化粧の表現と共に、指先の演出が生まれます。
そして中背ウヨーロッパの時代は、ハンマムと呼ばれた美容院で
クリームを用いて爪の手入れをしていたようです。
※ハンマム(hammam)とは
モロッコ四季のサウナと風呂をあわせたようなものをいい、スパの元祖。
現在もモロッコでは、いたるところに見られる。
爪の彩色の始まり
化粧すなわち爪の彩色の始まりは呪術的な意味合いを強く持っていました。
また、一方で、ミイラの爪に彩色が残っていたことや、古墳の死骸近くの
土やその人骨が赤く染まって発見された事から、朱(水銀朱)は防腐剤としての
効果があるという事を知って使っていたのではないかと思われます。
事実、古代において復活と再生、来世での霊魂の存在を信じ、
身分の高い者達の死骸を保存するべく、ミイラの爪にも朱の色を
施していました。
また、そのための薬品や化粧品が作られ発達をみることが出来たと
言われています。
更に古代エジプト時代にはスキンケアのような美容術や、
ヘアーカラーなどもあり、美容に関してはそこからギリシャ・ローマ時代へと
伝えられていきます。
当時は、爪の色が身分を表し、王と王妃は濃い赤、その他のものは薄い色しか
許されなかったと言います。
古代エジプト時代
ネイルに色を施すという歴史は古代エジプト時代(紀元前3000年以前)から
営まれてきたと言われます。
ネイルの技術というよりは化粧(手、顔、身体を含む全ての部位に対しての
菜食を施していく事)全般の中の一つの部位に対しての彩色として、
スタートしたと思われてます。
古代エジプト時代には、植物のヘンナの花の汁を用いて爪を染める風習が
ありました。
古代人は特に赤色を好んでいたといわれ、太陽の赤、血の赤をあらわし、
神聖な色として尊ばれていました。
更にエジプトの古い資料に第6王朝の頃に爪を清潔に保つ為のマニキュアを
男女共に行っていた記録があります。
マニキュアの語源
日本においてマニキュアとは、一般的に爪に塗るネイルエナメルの事と、
ネイルの施術の両方をさしています。
本来はラテン語の「マヌス」(manusu=手)と「キュア」(cure=手入れ)
からきた「手の手入れ」のことで、動揺にペディキュアは「ペディス」
(pedeis=足・キュア)が変化したもので「芦野手入れ」をさします。
1
ご予約・お問い合わせ
TEL : 03-5422-7017 (当日予約OK)
コースメニュー
MENU
カテゴリ